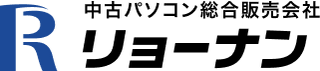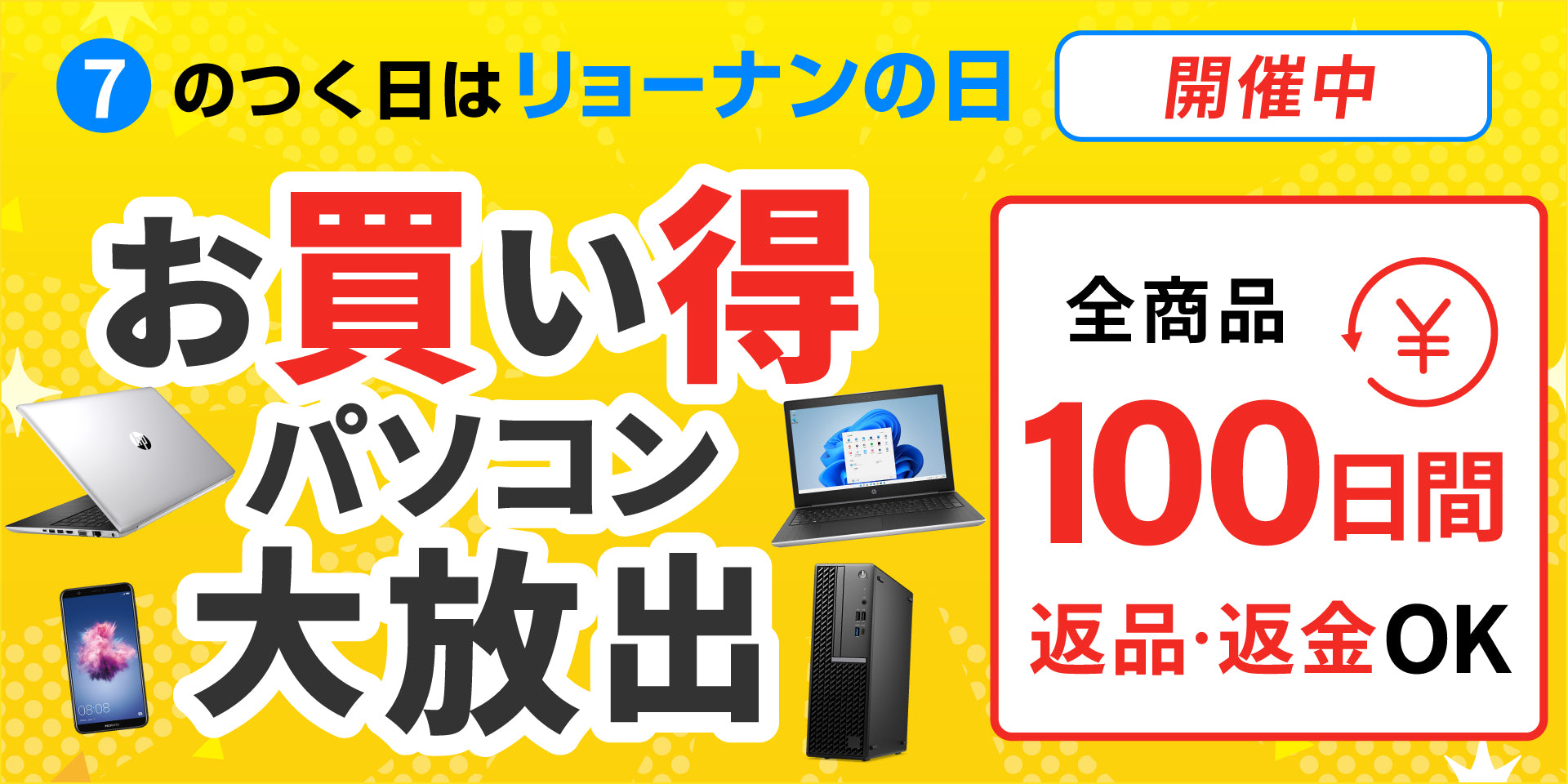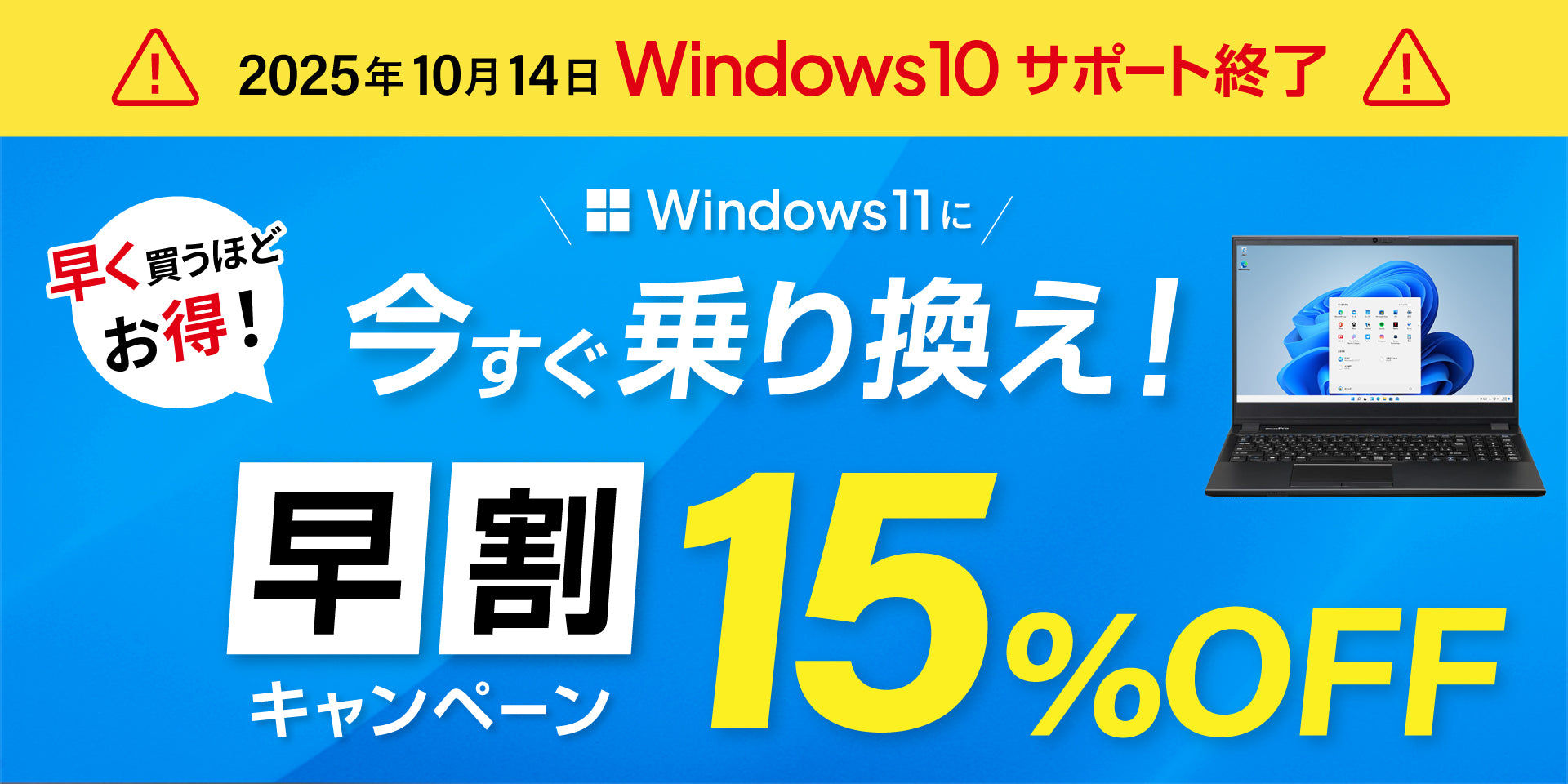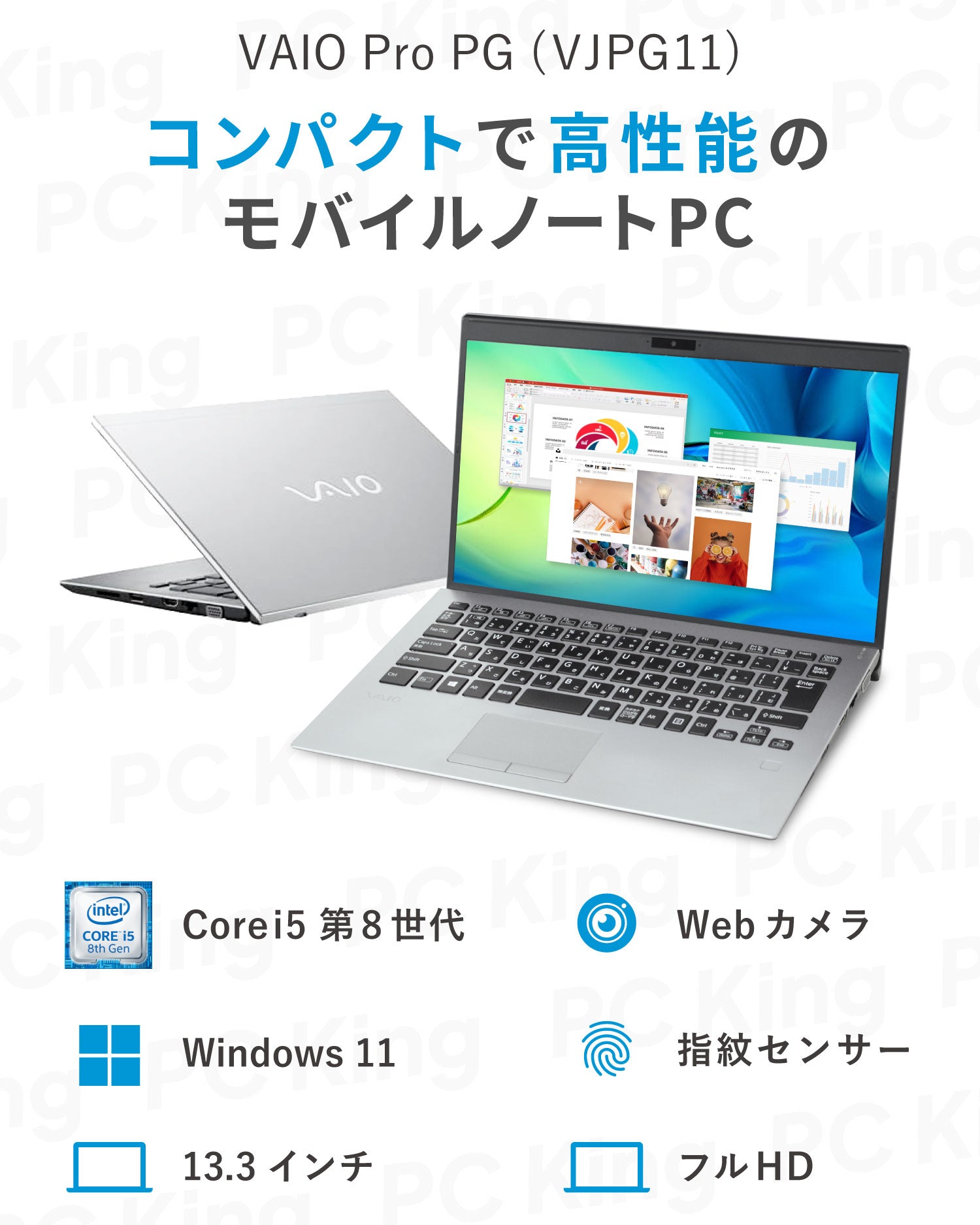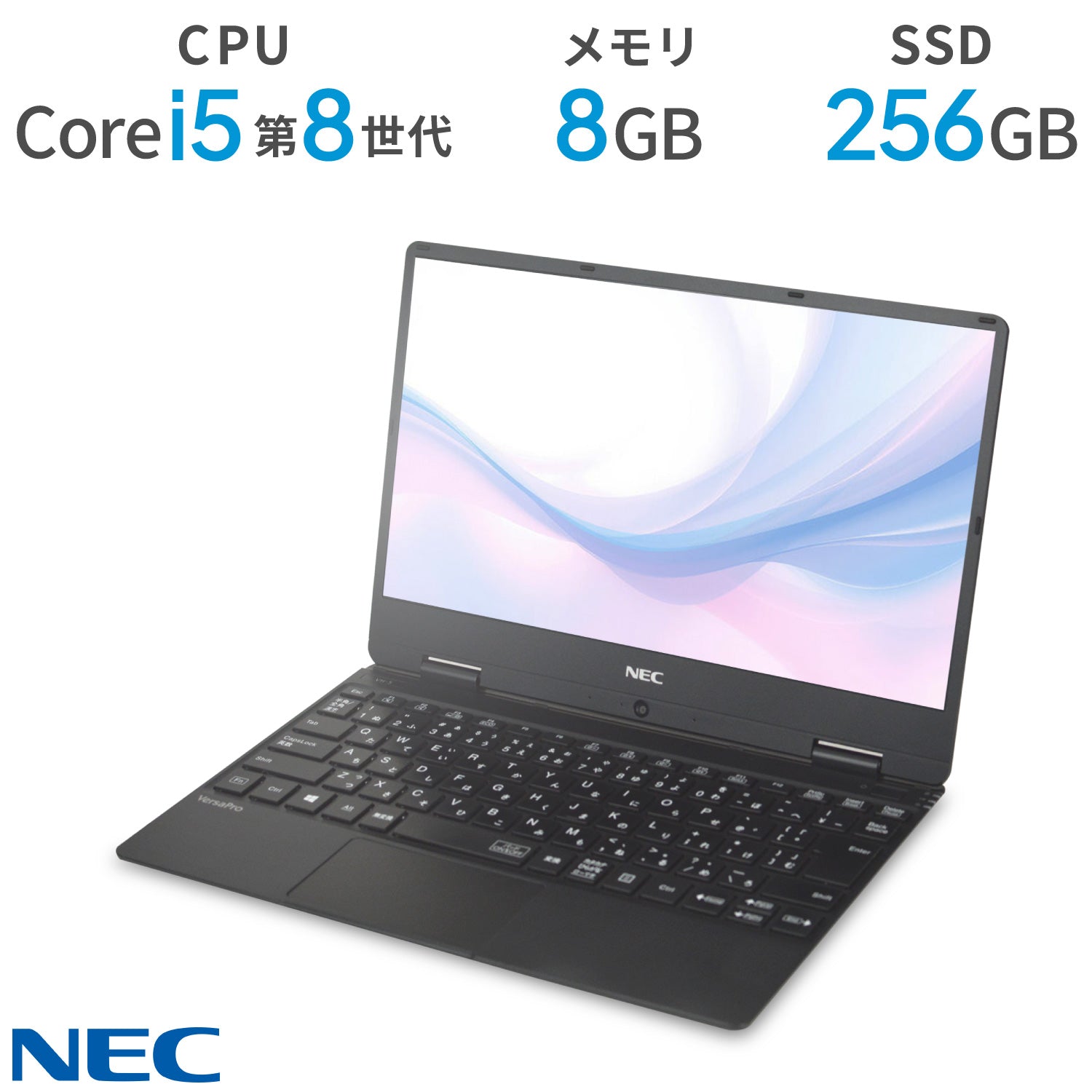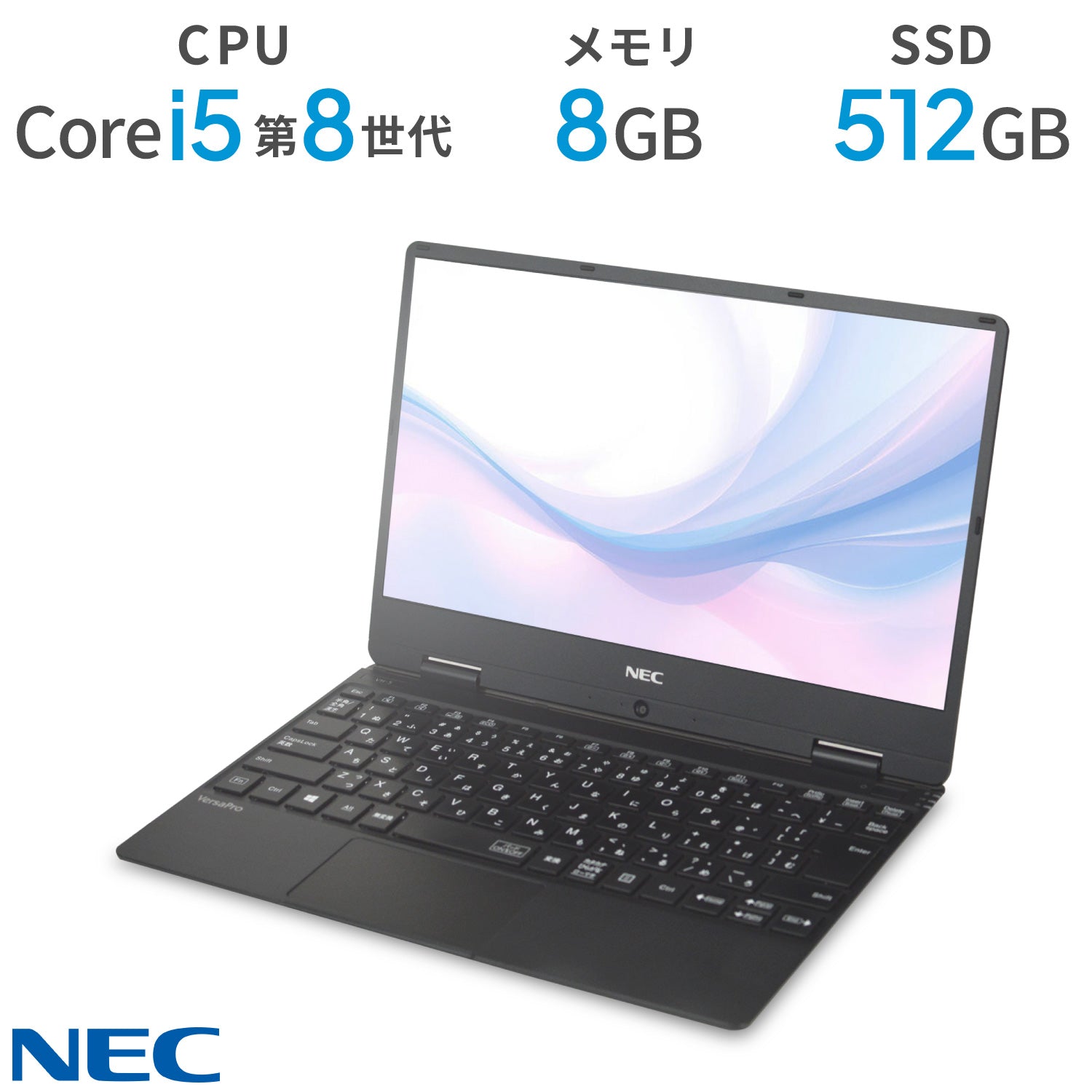目次
パソコンの安定動作を支える重要なパーツである電源ユニット。ただ適当に選んでしまうと、動作不安定やノイズの原因になってしまいます。この記事では、変換効率や静音性に優れた信頼性の高い電源ユニットの選び方と、用途別のおすすめモデルを紹介します。80PLUS認証やCybenetics認証の違い、容量の選び方から、実際の人気モデルまで詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
PC電源の重要性と選ぶ際のポイント
電源ユニットはPCの全てのパーツに電力を供給する心臓部とも言える存在です。安価な製品に手を出してしまうと、パソコンの不安定動作や最悪の場合、他のパーツの故障を引き起こす原因にもなります。
高品質な電源ユニットを選ぶことで、PCの長期安定稼働が期待できるだけでなく、電気代の節約や静かな作業環境の実現にもつながります。では具体的にどんなポイントに注目して選べばよいのでしょうか?
- 変換効率(80PLUS認証等のグレード)。
- 静音性能(ファンの種類、ファンレスモードの有無)。
- 必要十分な電源容量(W数)。
- 安全性・保護機能の充実度。
- ケーブル構成(フルモジュラー型など)。
これらのポイントを押さえることで、用途に最適な電源ユニットを選択できるようになります。特に変換効率と静音性は、長期間使用するパソコンの快適さを大きく左右する要素なので、しっかりチェックしましょう。
電源ユニットの効率規格の理解
電源ユニットを選ぶ際、まず目にするのが「80PLUS認証」などの効率規格です。これらの認証は、電源ユニットがどれだけ効率よく交流電力を直流電力に変換できるかを示す指標となります。
80PLUS認証の基本知識
80PLUS認証は、電源ユニットの変換効率を示す世界的な基準です。名前の通り、電源ユニットが少なくとも80%以上の変換効率を持つことを証明する認証制度になります。
認証には複数のグレードが存在し、変換効率が高いほど上位の認証を取得できる仕組みです。具体的には以下のようなグレードがあります。
| 認証グレード | 20%負荷時 | 50%負荷時 | 100%負荷時 |
|---|---|---|---|
| 80PLUS Standard | 80% | 80% | 80% |
| 80PLUS Bronze | 82% | 85% | 82% |
| 80PLUS Silver | 85% | 88% | 85% |
| 80PLUS Gold | 87% | 90% | 87% |
| 80PLUS Platinum | 90% | 92% | 89% |
| 80PLUS Titanium | 92% | 94% | 90% |
変換効率が高いほど無駄な発熱が少なく、結果として電気代の節約と静音性の向上につながります。一般的な用途ではGold以上がおすすめですが、予算と相談しながら選ぶとよいでしょう。
Cybenetics認証の登場と特徴
近年注目されている認証に「Cybenetics」があります。この認証は80PLUSとは異なり、変換効率だけでなく静音性も評価する点が特徴です。
Cybenetics認証では、変換効率はETA(Efficiency Typical Average)として6段階(ETA++からETA-)で評価され、静音性はLAMBDA(Linear Adaptive Modulation Bass & Acoustic noise Dampening Attenuation)として8段階(A++からD)で評価されます。
| ETA評価 | 平均効率 | LAMBDA評価 | 騒音レベル |
|---|---|---|---|
| ETA++ | ≥96% | A++ | 0~15dBA |
| ETA+ | 94~96% | A+ | 15~20dBA |
| ETA A | 90~94% | A | 20~25dBA |
| ETA B | 88~90% | B | 25~30dBA |
| ETA C | 85~88% | C | 30~35dBA |
| ETA- | 82~85% | C- | 35~40dBA |
| D+ | 40~45dBA | ||
| D | ≥45dBA |
静音性を重視する方は、LAMBDA評価がA+以上の製品を選ぶとよいでしょう。デスク周りで集中したい方には、静音性の高いLAMBDA A以上の製品がおすすめです。
適切な電源容量の選び方
電源ユニットの容量選びは、安定動作に直結する重要なポイントです。容量が不足していると、負荷時にシャットダウンが発生したり、パーツの寿命を縮める原因になります。
必要ワット数の計算方法
PCに必要な電源容量は、搭載するパーツの消費電力の合計で決まります。主要パーツの目安消費電力は以下の通りです。
- CPU:65~250W(モデルによる)。
- グラフィックカード:75~450W(モデルによる)。
- マザーボード:50~100W。
- メモリ:2~5W(1枚あたり)。
- SSD:3~10W(1台あたり)。
- HDD:5~10W(1台あたり)。
- ファン・LED等:5~30W(構成による)。
これらを合計した後、余裕を持たせるために計算結果の20~30%増しの電源容量を選ぶのが安心です。例えば計算結果が500Wなら、600~650W程度の電源ユニットを選びましょう。
最近のハイエンドGPUは瞬間的に大きな電力を必要とするため、特に余裕を持つことが重要です。また、将来のアップグレードも考慮するなら、さらに余裕を持たせておくとよいでしょう。
用途別の推奨電源容量
一般的な用途別に推奨される電源容量を紹介します。もちろん、実際の構成によって必要な容量は変わりますので、前述の計算方法で確認することをお忘れなく。
| 用途 | 推奨容量 | 想定構成例 |
|---|---|---|
| 一般事務・Web閲覧 | 400~500W | Core i3/i5、内蔵グラフィック、SSD、RAM 16GB程度 |
| エントリーゲーミング | 550~650W | Core i5/Ryzen 5、RTX3060/RX6600XT程度、SSD、RAM 16GB |
| ミドルゲーミング | 650~750W | Core i7/Ryzen 7、RTX3070/RX6700XT程度、SSD、RAM 32GB |
| ハイエンドゲーミング | 850~1000W | Core i9/Ryzen 9、RTX3080/RX6800XT以上、SSD、RAM 32GB以上 |
| クリエイター向け | 850~1200W | Core i9/Ryzen 9/ThreadRipper、RTX4080/4090、複数SSD、RAM 64GB以上 |
最新のGPUやCPUは高性能化とともに消費電力も増加傾向にあります。とくにRTX4000シリーズやRX7000シリーズのグラフィックボードを使用する場合は、十分な余裕を持った電源容量の確保が必須です。
静音性にこだわる電源ユニット選び
作業環境の快適さを左右する静音性。電源ユニットは24時間稼働するパーツだけに、静かさを重視する方も多いでしょう。静音性の高い電源ユニットの特徴を見ていきましょう。
ファンレスモードとは
高品質な電源ユニットに搭載されている「ファンレスモード」(ゼロRPMモード、セミパッシブモードとも呼ばれます)は、低負荷時にファンを停止させる機能です。
一般的なPC使用時は電源ユニットのファンが完全に停止するため、静かな作業環境を実現できます。負荷が高まると自動的にファンが回転を始めるため、冷却性能も確保されています。
ファンレスモードを搭載した電源ユニットは、静かな環境で作業したい方に最適な選択肢です。デスクワークや動画編集など、静かな環境で集中したい作業におすすめです。
静音設計の電源ユニット特徴
静音性の高い電源ユニットには、以下のような特徴があります。
- 高品質な大口径ファン(120mm~140mm)の採用。
- 流体軸受け(FDB)ファンの採用。
- 負荷に応じたインテリジェントなファン制御。
- 内部設計の最適化による風の流れの改善。
- 高品質コンデンサーの採用による振動・コイル鳴きの抑制。
静音性を示す指標としては、前述のCybenetics認証のLAMBDA評価が参考になります。また、製品スペックに記載されている騒音値(dBA)も比較の目安になります。
例えば、25dBA以下であれば図書館程度の静かさで、非常に静音性が高いと言えます。30dBA以下でも十分静かで、デスクワーク環境には問題ないレベルです。
ケーブル管理が楽なモジュラー電源
電源ユニットを選ぶ際、もう一つ重要なポイントがケーブル構成です。ケースの内部をすっきりと管理できるモジュラー電源が人気を集めています。
モジュラータイプの種類と違い
電源ユニットのケーブル構成は大きく3種類に分けられます。
- 固定式(ノンモジュラー):すべてのケーブルが電源本体と一体になっているタイプ。
- セミモジュラー:マザーボード用の24ピン・CPU用の8ピンなど必須ケーブルは固定で、その他のケーブルは着脱可能。
- フルモジュラー:すべてのケーブルが着脱可能なタイプ。
モジュラータイプは必要なケーブルだけを接続できるため、内部の配線がすっきりして冷却効率アップにも貢献します。不要なケーブルを接続しないことで、ケース内部の風の流れが改善され、結果的に冷却性能が向上します。
特にミドルタワー以下のケースや、ケーブル収納スペースが限られたケースでは、モジュラー電源の恩恵が大きいでしょう。見た目もすっきりするので、透明サイドパネルのケースとの相性もバツグンです。
ケーブル本数とコネクタ数を確認
電源ユニットを選ぶ際は、必要なコネクタの種類と数をしっかり確認しましょう。特に重要なのは以下のポイントです。
- マザーボード用24ピン電源コネクタ(必須)。
- CPU用8ピン(4+4ピン)電源コネクタ(ハイエンドCPUでは8+8ピンが必要な場合も)。
- グラフィックカード用PCIe 8ピン(6+2ピン)電源コネクタ(高性能GPUでは複数必要)。
- SATA電源コネクタ(SSD・HDDの数に応じて)。
- ペリフェラル(Molex)コネクタ(ファンコントローラーなどに使用)。
最新のハイエンドグラフィックカード(RTX4000シリーズなど)では、新しい12VHPWR(12+4ピン)コネクタが採用されているものもあります。これに対応した電源ユニットや、変換アダプタの有無も確認しておくとよいでしょう。
用途別おすすめPC電源ユニット
ここからは、実際に市場で人気のある電源ユニットを用途別に紹介します。効率性、静音性、価格のバランスを考慮したおすすめモデルをピックアップしました。
コスパ重視のミドルレンジモデル(550~650W)
一般用途やエントリー~ミドルクラスのゲーミングPCに最適な電源ユニットです。性能と価格のバランスが取れた製品を集めました。
-
Corsair RM550x(2021)
- 80PLUS Gold認証。
- フルモジュラー設計。
- ファンレスモード搭載。
- 静音性の高い140mmファン採用。
- 日本製コンデンサー採用で高い信頼性。
- 価格帯:12,000円前後。
-
be quiet! Pure Power 11 FM 650W
- 80PLUS Gold認証。
- フルモジュラー設計。
- 静音性に定評のあるbe quietブランド。
- 120mmサイレントウイングスファン。
- 5年保証付き。
- 価格帯:11,000円前後。
-
Seasonic FOCUS GX-650
- フルモジュラー設計。
- ハイブリッドファンモード搭載。
- 高い信頼性で知られるSeasonicブランド。
- 10年保証付き。
- 価格帯:12,000円前後。
この価格帯では、80PLUS Gold認証とフルモジュラー設計の両立がコスパのポイントです。特にRM550xとFOCUS GX-650は長期保証が付いており、長く使えることを考えると実質的なコスパは高いと言えるでしょう。
ハイエンド向け高効率モデル(750~850W)
高性能なグラフィックカードを搭載したゲーミングPCやクリエイター向けPCに適した電源ユニットです。効率性と安定性に優れたモデルを紹介します。
-
Corsair HX850
- 80PLUS Platinum認証。
- フルモジュラー設計。
- ファンレスモード搭載。
- 高品質日本製コンデンサー採用。
- 10年保証付き。
- 価格帯:19,000円前後。
-
be quiet! Dark Power 12 750W
- 80PLUS Titanium認証。
- フルモジュラー設計。
- 超静音135mmサイレントウイングスファン。
- フルブリッジLLC共振型コンバーター採用。
- 10年保証付き。
- 価格帯:26,000円前後。
-
Seasonic PRIME TX-750
- 80PLUS Titanium認証。
- フルモジュラー設計。
- ハイブリッドファンモード。
- 業界トップクラスの変換効率。
- 12年保証付き。
- 価格帯:25,000円前後。
ハイエンドモデルでは、Platinum以上の高い変換効率と長期保証が魅力です。特にTitanium認証を取得した製品は、低負荷時の効率も高いため、作業をしない時間が長いPCでも電気代の節約効果が期待できます。
超高性能マシン向け大容量モデル(1000W以上)
最新のRTX4090やRadeon RX7900XTXといった超高性能GPUを搭載したり、複数GPUを使用する場合に適した大容量電源ユニットです。
-
Corsair AX1600i
- 80PLUS Titanium認証。
- フルモジュラー設計。
- デジタル制御によるきめ細かな電圧安定化。
- iCUEソフトウェア対応で電力モニタリング可能。
- ファンレスモード搭載。
- 10年保証付き。
- 価格帯:60,000円前後。
-
be quiet! Dark Power Pro 12 1200W
- 80PLUS Titanium認証。
- フルモジュラー設計。
- 135mmサイレントウイングスファン。
- OCKスイッチで単一12Vレールと複数レールの切り替え可能。
- 10年保証付き。
- 価格帯:40,000円前後。
-
Seasonic PRIME TX-1000
- 80PLUS Titanium認証。
- フルモジュラー設計。
- ハイブリッドファンモード。
- 超高効率設計。
- 12年保証付き。
- 価格帯:35,000円前後。
超高性能マシン向けの電源ユニットは高価ですが、長期保証と高い信頼性が最大の特徴です。高額なパーツを保護する役割も持つため、この価格帯ではコストよりも品質を重視して選ぶことをおすすめします。
静音性重視の厳選モデル
静かな作業環境を実現したいユーザーのために、特に静音性に優れた電源ユニットを紹介します。
-
be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W
- 80PLUS Platinum認証。
- フルモジュラー設計。
- 静音設計で定評のあるbe quietブランド。
- 135mm サイレントウイングスファン。
- ファンレスモード搭載。
- 価格帯:18,000円前後。
-
Corsair RMx SHIFT 750W
- 80PLUS Gold認証。
- フルモジュラー設計。
- 設置方向に関わらず接続が容易なサイドコネクタ。
- 140mm FDBファン採用。
- ファンレスモード搭載。
- 価格帯:16,000円前後。
-
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W
- 80PLUS Platinum認証。
- フルモジュラー設計。
- 140mm FDBファン採用。
- UltraFlexケーブル採用で配線が容易。
- ファンレスモード搭載。
- 価格帯:17,000円前後。
これらの製品は、いずれもファンレスモードを搭載し、低負荷時に完全無音で動作することが大きな特徴です。また、ファンが回転する場合でも、高品質なファンを採用しているため、騒音レベルは極めて低く抑えられています。
電源ユニットの寿命と保証期間
電源ユニットは経年劣化するパーツであり、選ぶ際には寿命と保証期間も重要なポイントです。高品質な電源ユニットは長期保証が付いていることが多く、それだけメーカーが自社製品に自信を持っている証でもあります。
電源ユニットの一般的な寿命
電源ユニットの寿命を左右する主な要因は以下の通りです。
- 使用コンデンサーの品質。
- 動作温度(涼しい環境ほど長寿命)。
- 負荷率(容量に余裕があるほど長寿命)。
- 電源品質(電圧変動が少ない環境ほど長寿命)。
一般的に、高品質な電源ユニットは7~10年程度の使用に耐えられるように設計されています。日本製コンデンサーを採用した製品や、105℃対応のコンデンサーを使用した製品は、特に長寿命が期待できます。
電源ユニットの寿命を延ばすには、実際の消費電力よりも余裕のある容量の製品を選ぶことが効果的です。例えば500W程度の消費電力なら、750W程度の電源ユニットを選ぶと、負荷率が下がり、結果的に長寿命化につながります。
主要メーカーの保証期間比較
メーカー・シリーズごとの一般的な保証期間を比較してみましょう。
| メーカー | シリーズ | 保証期間 |
|---|---|---|
| Corsair | AXi/HXi/AX/HX | 10年 |
| RM/RMx | 10年 | |
| CX/CV | 5年 | |
| be quiet! | Dark Power Pro | 10年 |
| Straight Power | 5年 | |
| Pure Power | 5年 | |
| Seasonic | PRIME | 12年 |
| FOCUS | 10年 | |
| ASUS | ROG THOR | 10年 |
| TUF Gaming | 6年 |
保証期間が長い製品は一般的に価格も高くなりますが、長期間使用することを考えると、年あたりのコストは意外と安くなる場合があります。長期的な視点で選ぶなら、10年以上の保証がある製品がおすすめです。
まとめ
PC電源ユニットは、パソコンの安定動作と長寿命を支える重要なパーツです。高効率で静音性の高い電源ユニットを選ぶことで、電気代の節約や快適な作業環境の実現につながります。
選び方のポイントをまとめると、まずは80PLUSやCybenetics認証などの効率規格を確認し、Gold以上の高効率モデルを目指しましょう。容量は実際の消費電力より20~30%以上余裕を持たせること、そしてモジュラータイプを選ぶとケーブル管理が格段に楽になります。静音性を重視するなら、ファンレスモード搭載モデルやbe quietなどの静音設計で定評のあるブランドがおすすめです。
また、長期間使用することを考えるなら、10年以上の長期保証がついたモデルを選ぶことで、結果的にコストパフォーマンスも向上します。あなたのPCの用途や予算に合わせて、最適な電源ユニットを選んでみてください。